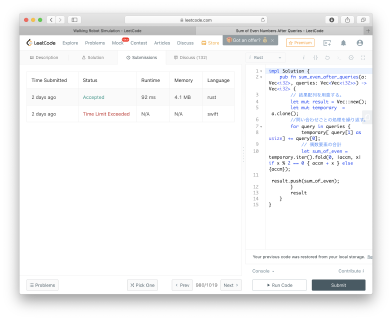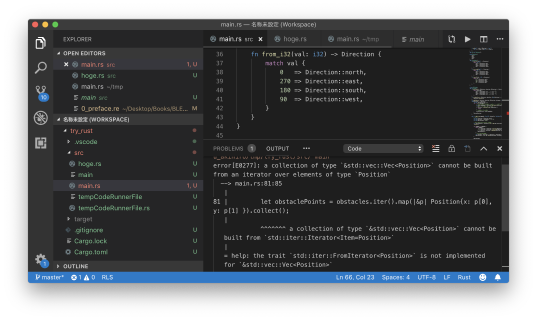はじめに
BLE本の執筆を開始しようと思い、手始めに思うところを徒然と書いてみようかと思います。童話で、井戸に向かって、人に言えない秘密を大声で叫ぶ、王様の耳はなんとやらのお話がありますが、その井戸に叫ぶようなところです。
本というものは客観的に書かないと商品にならないのですが、そんな客観的な文章を書いていると、頭の後ろ側がヒリヒリとかゆくなって、続かないので、ここで主観しかないことを書いて、バランスを取ろうというのが目的です。
なので、読ませるための文章じゃありません。どこかの飲み屋さんでお酒を飲むか、タバコでも吸いながら愚痴として空気に霧散させるのが、よいのでしょうが、あいにくお酒もタバコも嗜みませんし、リアル世界に話す人間もいませんから、ネットにこうやって霧散させようというわけです。
ならツイッターに流せばと思われるかもですが、ツイッターは幸福で幸せな日常で彩りたいのですよ。どこか知らない人のタイムラインに、ある日突然3分ごとにツイートが連続して流れ出して、それがこれから下の内容だったらとか思ってみてくださいよ。幸せじゃないじゃないですか。
フリーランスする言い訳がなくなりまして
昨年、両親が他界しまして。
この10年ほどフリーランスをやっていた自分向けの理由が、もしも両親が病気で倒れても即座に対応できる、会社勤務だと有給を使い切ったら休職なり辞めるなりで大騒ぎだけど、元々がフリーランスならそんな事もないでしょう、という立派な理由でした。
10年前に会社を辞めたのは、5月の朝とても気持ちがいい晴天で、こりゃ会社行っている場合じゃないなと思ったからで、そのあとフリーを始めたのは、毎日会社に行くのがめんどくさいからなので、こんな立派な理由はただの言い訳なのですが、そんな理由もそもそもがなくなってしまいまして。
さて、こうなると自分の生き方は自分で決めなさいになるわけですが、身軽過ぎて、これがまた身の置き所に困るわけです。子供がいるわけでも、会社のしがらみがあるわけでもない。徹底的に気楽さを追求しているので、自分がすることは自分で探して決めるほかないわけです。で、ざっと周りを見渡してみると、いろんな生き方があるなーとは思うけど、どれも当事者になりたい気はしないわけです。
iOSアプリやBLEのファームウェア開発、あるいは組み込み系の開発で開発を個人で請け負うなんて、仕事になるのかと思われるでしょうが、実際のところ月に100~400万円くらい売り上げができるわけです。
短いお仕事なら2ヶ月くらい、長いお仕事だとそれでも1年単位くらいで、フリーランスという名前の通りに、必要な技能を提供して必要とされる成果物を収めたら、そこで完了という、そういうお仕事です。
本気で3ヶ月も働くと、指先の皮はキーボードとの摩擦とストレスでボロボロと剥がれて、皮が薄くなって血が滲むので、湿潤治療の絆創膏を皮膚がわりに貼り付けてしのぐ、そんなのを一年ずっと続けられるわけもないので、働くのは一年に1ヶ月を3回くらいが、ほどほどでしょう。
ですから一年のうち3ヶ月も働いたら、日本の地方都市での生活費用(年金や保険と税を抜いて400万円もあれば十分でしょう)くらいは満たせるので、それ以上働くのか?といえば、そこに働く気も起きないわけです。ただ、おもしろいお仕事だと、おもしろいので、つい話を聞きに行っちゃいますが。
なので、必要を超えて働く理由も、あまりないわけですよ。
プロなら自分で勉強するでしょう
組み込みをやっていてBLEがわからない、いい本がないか?とか言われたら、無言でBLE handbookを差し出すわけですよ。あれはBLEの規格を制定したグループのCSR勤務の副議長、本当のプロ中のプロが書いている本ですから。
プロとしてのお仕事は、結果保証なところがありますから、目の前のものが動いているやったーなんて趣味じゃなくて、動いている理由をマイクロ秒単位でビット単位でμA単位で、物理と規格に基づいて完全説明できて、だから動きますよといえないと、怖くて収められないわけですよ。
だから、必要な情報をちゃんと習得できないのに仕事なんか受けられるわけがないでしょう。仕事なのですから。英語が読めないとか、分厚すぎるとか、そんなの、それがどうした? できないなら手がけるな、なんですよ。
実際に私の場合で、4ヶ月くらいですか、BLE handbookとBluetoothの規格書とNordicの半導体のドキュメントとSDKを、じっと睨んで動かして理解してを繰り返してました。本当、ちゃんとプロに教われば1ヶ月くらいでいいらしいですけど、独学で時間を無駄にしているところが、馬鹿っぽくって私らしいですね。
それでも、書くのが好きなようで、BLEの解説をちょっとブログに書くと、リアルで、あれ読みやすかったよとか、分かり易かったとか言われるわけです。やっぱりそう言われると、嬉しくなっちゃうもので、ようし、もうちょっと書こうかなと言っちゃうわけです。
そして机の前に座ると、そんなお調子よく言っている気持ちも30秒で吹き飛ぶのです。だって、BLEって無線からタイミングからプロトコルからデータ表現まで含んだ、完全な無線通信で何かの機能と振る舞いを丸っと実装できる技術体系そのものですよ。今時、話題のIoTの解説本でも、イーサネットの物理層ならイーサネット単体で、IP層ならTLSも含めるかもですけどトランスポート層までで、MQTTなりOAuthなりアプリ層はアプリ層で、層ごとにとかもっと細かい細分で、もう300ページの本になっているわけですよ。
BLEで、層の内容は薄いけど、それらの層を全部含んでいるわけですよ。それを解説を書こうとするわけですよ。BLEの副チェアマンが書いても400ページ行くような、そんなものなんですよ。なんで、勉強しただけの素人な私に、そんな分野の丸っとした本が書けると思うねん? って冷静になるわけですよ。
だいたい1日に書ける文字数が1万文字、10ページとして書くだけで1ヶ月、技術本って裏付けや調査に時間がかかるから、よく知っている分野でも1つ1つ確かなことかを文献にあたって確認して行くので、どうやっても半年は丸っとかかるくらいの、情報収拾と文章表現に時間がかかります。
その数ヶ月の道のりに、一歩足を乗せては、冷静になるわけですよ。2日くらいで書けるBLEの解説が分かり易かったと褒められて嬉しくて、時間もあるから書こうとする、でもここから数ヶ月かかるわけです。しかも想定読者は、自分と同じような仕事をするプロでしょ。
本音で言えば、同業らのために解説の仕事する義理も理由もないわけですよ。ファームウェアなら3ヶ月800万円で見積もり出すから、それで開発して納品するから、本とかそれ以前に、うちに発注すればいいわけですよ。世の中、お金でち。
なので、書く理由もなくなっちゃうわけですよ。
執筆の目線を勘違いしてたんでしょうね
そんなこんなで、2012年にちょっとBLE解説本を書いてみては、これじゃないなーと出版せずにいたわけです。BLEの技術更新は恐ろしく劇的で、そんなことしているうちにBluetooth4.0は、今や5.1が出ようとしています。高速化、ロングレンジ化、アドバタイジングの高度化にペイロード拡張と、もうやりたい放題で規格が毎年何かしら更新されるわけですよ。
見てて楽しいけど、4.0からの技術更新は後方互換性を維持してやっているから、4.0の技術じゃ動かない作れるものも作れちゃうし、それをすると、どの端末だと動かない?とか把握が必要になるしで、見たくもない地獄を見える目にあうわけですよ、リアル仕事だと、いい加減にしろこの野郎です。せめて後方互換性をいっそのこと捨ててくれたらと思いますけど、それはそれで、キッツいんですよね…仕事したら負けだと思います。
でもね、ちょっと目線をずらすと、BLEの本が必要な場面かもなーというのが、この頃見えてきたと思いまして。要は、想定読者を組み込みやらiOSアプリやらの開発者としてたのが、こんな面倒くさい事を考え出すようになった、原因なんですよ。同業者なら、自分と同じように勉強しろ、効率最悪でも4ヶ月あればできるようになるから、と思っちゃうという。
でもね、BLEって、サービスで関わる人もいるし、事業立案で使う人もいるし、開発もアプリとファームとハードウェアと、担当者が別の人でチームで仕事してたりするわけですよ。そうすると、ファーム書く人が理解している、というだけじゃ、トラブルわけです。アプリとかもっと言えば事業とかと、目線があって同じような言葉で同じように話せてないと、仕様も作れないわけです。
そういう考え方をすると、あ、これ海外旅行に行く人の簡単会話集的な位置付けの本がいるんだなって思いました。BLEという言葉のあるところを旅行するためには、BLEというものの文法や単語がわかれば話し言葉が組み立てられますよね、BLEを使う分野で危ないところや安全なところを事前に知っていれば目的地まですっと移動できますよね、そういう目線で見たBLEの解説なら、同業者じゃなくてチーム向けの本として、ありでしょう。
チーム向け、BLEという外国語でBLEという外国を旅するための言語解説込み込みのガイドブック。これなら、書く意味も見いだせるわけです。なぜなら、こんな本を書いた人ならBLEの開発のお仕事を依頼したいという、名刺になりますから。私のところに仕事が来なくても、それはそれで同業向けに書いた本じゃないわけですから、自分の本で自分にきたかもしれない仕事を削り落としたのかと疑心暗鬼にならずにもすむのです。たぶんね。
価格はわふーにちなんで1.2万円
と、2012年から7年余りで、やっと書く気になったわけですが、価格だけはもう、わふーにちなんで1.2万円と決めておきましょう。Kindleでも電子でも紙でも、どんな媒体でも、1.2万円です。買いやがれコンチクショー、です。
では、また執筆状況が進めば、ここに吐き出しにくると思いますので。